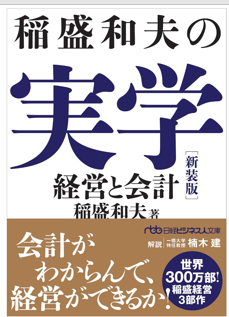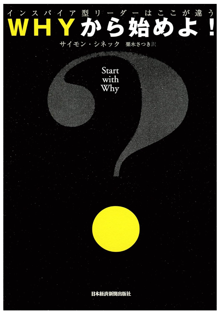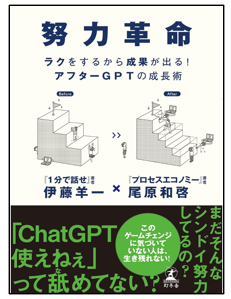『名古屋商科大学ビジネススクール
ケースメソッドMBA実況中継 01
経営戦略とマーケティング』
牧田幸裕(著)
ディスカヴァー・トゥエンティワン(2020/3/20) 2,750円 – (現在はKindle版のみ)
【感想】
著者は経営戦略・マーケティング分野を専門とする研究者・実務家です。京都大学経済学部を卒業後、同大学大学院経済学研究科を修了。ハーバード大学経営大学院エグゼクティブ・プログラム(GCPCL)も修了しています。アクセンチュア戦略グループ、サイエント、ICGなど外資系コンサルティング企業においてディレクター、ヴァイスプレジデントを歴任し、企業の成長戦略や営業改革に携わりました。2003年に日本IBMへ移籍し、エレクトロニクス業界や消費財業界を中心にクライアント・パートナーとして活躍。複数の大学院で教育・研究に従事。実務と理論を架橋する視点から、戦略思考やマーケティングの重要性を発信し続けています。
本書は、私の母校である名古屋商科大学ビジネススクールが発刊した書籍であり、経営戦略とマーケティングの原理原則を、ケースメソッドという体験型の手法を通じて伝える一冊です。実際の授業では、この本の何倍もの緊張感があり、次に何を問われるかわからない状況の中で、頭から汗が噴き出るような思考を強いられます。正直、かなりしんどいです。一方で本書は、紙面から緊張感は伝わってくるものの、腰を据えて冷静に読むことができ、自分なりに考える余白も残されています。
本書の特徴はケースメソッドによる疑似体験にありますが、それ以上に価値があるのは、経営戦略とマーケティングにおける原理原則を徹底して扱っている点です。経営書の多くが「今すぐ使えるHow to」に傾きがちな中、本書に書かれている内容は、読んですぐに成果が出る類のものではありません。しかし、ここで示される考え方を理解し、日々の経営判断に粘り強く落とし込んでいくことで、時間をかけながらも確実に会社を強くしていく道筋が描かれています。本書の内容を日々の経営に活用してみてはいかがでしょうか?
【以下、引用】
3Cとは、市場、競合、自社である。その分析の手順は、「市場、競合、自社の順番で分析する」だ。
・・・・・・・
3C分析の目的は大きく分けると2つある。
ひとつは…「市場の変化に対応している競合企業を見習い、自社の改善ポイントを明らかにする」ことである。もうひとつは、「市場の変化や競合の対応を見たうえでビジネスチャンスを見つけ出し、いち早くそのチャンスをつかみ自社を成長させる」こと。言い換えれば、「自社が突き抜けるにはどうしたら良いのかを考える」ことである。
・・・・・・・
3C分析で明らかにしたいことは以下の通りだ。
1.市場の変化を明らかにし、その市場での成功要因を明らかにする
2.市場の変化と成功要因に対する競合の対応を明らかにし、競合企業の成功のキモを明らかにする
3.競合企業を見習い自社の改善ポイントを明らかにする