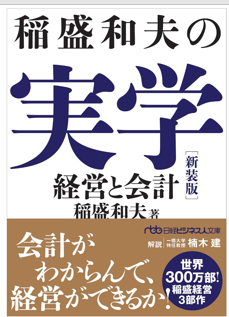あいさつ
大澤賢悟です。新年、あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。「一年の計は元旦にあり」と言われるように、年の始まりは、これからの一年をどのように歩むかを考える大切な節目です。会社においても、今後一年間をどのような戦略で進んでいくのかを、このタイミングでしっかりと定める必要があります。
弊社では毎年、経営計画書を作成していますが、その中では向こう一年間の重点テーマを明確にしています。弊社の向こう一年間の重点テーマは、「重要だが緊急でない領域の強化」です。今年は、「重要だが緊急ではない領域」への投資を優先し、サービスのR&D(ブラッシュアップ)と広告宣伝(マーケティング)を事業戦略の中心に据えて取り組みます。
【R&D】
既存のPDCAサイクル(C:財務、P:コーチング、C・P:ビジネスモデルキャンバス)を基盤としながら、より価値の高いサービスへ進化させることを目指す。特に、コーチング分野では「計画が実行されにくい」という課題が必要である。併せて、ビジネスモデルやマーケティング効果を俯瞰的に把握できるようフレームワークと連携し、サービス全体の価値向上につなげる。市場調査については、Googleの各種サービスを活用し、データに基づいた分析と改善を継続する。
【広告宣伝】
複数のSNSを通じて、情報発信を強化する。また、一般層の興味を引く記事や書籍の制作にも取り組み、認知拡大を図る。さらに、Googleを活用したHPアクセス解析を行い、実際のデータに基づく効果的なマーケティング施策を計画・実行する。
【AI・自動化の活用】
R&Dやマーケティング活動を支える基盤として、AIを積極的に活用する。ノーコードツールとAI技術を組み合わせ、業務の自動化を推進するとともに、これらの技術を将来的に自社サービスの一部として体系化することも視野に入れる。Googleのサービスやシステムも活用し、効率性と品質を兼ね備えたサービス提供体制の構築を目指す。
【外部連携の強化】
関連士業との関係構築については、本年も継続して強化を図る。また、保険会社や金融機関など、周辺専門家との協業可能性についても検討し、提案活動を進めていく。
日々の業務に追われると、どうしてもこのような業務は先送りになりがちです。あえて明示することで、やらないといけないと追い込んでみました。1年、頑張ります。
今年も税制大綱が発表されました。詳細な内容については別紙に譲りますが、故安倍元首相の路線を受け継ぎつつ、高市総理の積極的な政策姿勢が随所に感じられる内容となっています。足元では日経平均株価も上昇を続けており、市場には明るいムードが広がっているようにも見えます。しかし、実体経済の裏付けが伴わなければ、それは単なるバブルに過ぎません。では、この流れは一過性のものなのか、それとも本物の成長へとつながっていくのでしょうか。さて、1年後の日本経済、そして私たちを取り巻く環境は、どのような姿になっているでしょうか。
10人に1人は相続税の対象者
弊社では、日頃から相続に関するご相談や申告業務を数多く取り扱っていますが、そうした実務感覚とも重なる興味深い記事が、日経新聞に掲載されていました。2024年に亡くなった方のうち、相続税の課税対象となった割合が10.4%と、初めて「1割」を超えたという内容です。数字だけを見ると、もはや相続税は「一部の富裕層の話」とは言えなくなってきています。
背景にあるのは、2015年の基礎控除引き下げに加え、地価の上昇、そして少子高齢化による相続人の減少です。財産総額が同じでも、受け取る人数が少なければ、課税ラインを超えやすくなります。制度と社会構造の変化が、静かに相続税の裾野を広げています。
実際、相続財産の内訳を見ると、現金・預貯金と土地が大きな割合を占めており、「普通にまじめに生きてきた結果」が、そのまま課税対象になっている印象も受けます。一方で、調査件数や追徴税額も過去最多となっており(実地調査と簡易な接触を合わせた調査件数は3万1481件、実地調査による追徴税額は824億円と過去10年で最多)、無申告や海外資産の申告漏れに対する目も、明らかに厳しくなっています。
現金を自宅に隠した脱税では重加算税まで課されるケースもあります。「知らなかった」「相談しなかった」では済まされない時代に入っている、というメッセージを、国税庁があえて数字で示してきた、とも言えるでしょう。
ホワイトカラーだけではない——AIロボが広げる現場レベルの雇用転換
AIの話がいよいよ「画面の中」だけのものではなくなってきています。その象徴的な例が、日立製作所によるヒト型AIロボットの自社工場導入です。
これまでAIというと、事務作業の効率化や資料作成、データ分析など、どちらかといえばパソコンの中の仕事を置き換える存在として語られることが多かったように思います。しかし日立の取り組みを見ると、AIはすでに工場の現場に入り込み、人間の動作を学習し、配線作業などの物理的な工程まで担おうとしています。しかも、生産ラインを大きく変えずに導入できるという点は、「一部の実験」ではなく、現実的な選択肢として検討されていることを示しています。現時点での目的は人手不足対策でしょう。ただ、この流れは本当にそれだけで終わるのでしょうか。
というのも、KPMGインターナショナルの調査で、日本の経営者の18%がAI対応による人員削減を「1年以内に計画している」と回答しています。さらに、「AIによる雇用への影響は最小限」と答えた経営者はゼロでした。
多くの経営者が、AIは単なる補助ツールではなく、人員配置そのものを見直す前提になりつつあると考えていることがうかがえます。
これまで人員削減の話は、事務職やホワイトカラーを中心に語られることが多くありました。ところが、ヒト型ロボットが現場作業を担えるようになれば、削減の対象はパソコンの前に座る人だけにとどまらなくなります。最初は人手不足を補う存在として導入され、やがて「人がいなくても回る工程」が増えていく。その結果、現実世界の職場でも、静かに人員削減が進んでいく可能性があります。
AIやロボットは、ある日突然仕事を奪うわけではありません。まずは「助ける存在」として入り込み、気づけば「人がいなくても成り立つ状態」を作り出す。日立の事例は、その変化がすでに現場レベルで始まっていることを示しているように思えます。
アメリカがベネズエラに対して電撃的な軍事行動に踏み切りました。ロシア・ウクライナ戦争は長期化し、パレスチナ・イスラエル戦争も出口が見えないままです。中国は軍事活動を一段と活発化させました。日本はアメリカの要望もあり、防衛費が増加していますが、今後、戦争に巻き込まれていくのでしょうか?
ダウンロードはこちらから