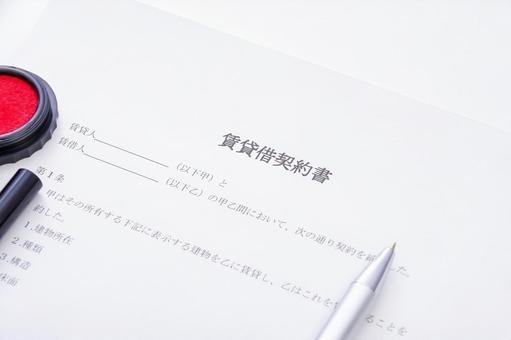法人と個人における暗号資産取引の税務
法人であれば、暗号資産取引の結果は法人の収入・損失となるため、
とくに考慮する必要はありません。
しかし、個人の場合、雑所得となるか、事業所得となるかは
大きな違いがあります。
事業所得であれば、赤字の際に他の所得との損益通算が可能です。
暗号資産取引の分類:雑所得と事業所得
基本的には雑所得に分類される暗号資産取引ですが、
その取引が商業活動と考えられるレベルなら事業所得になる可能性があります。
事業と認められる基準は、
暗号資産取引の収入が300万円以上であり、取引の帳簿を保持していることです。
帳簿を作成する場合は、総勘定元帳の作成が税務署対策に推奨されます。
事業に付随する取引の場合
また、取引が事業に付随して行われている場合も事業所得に該当する可能性があります。
たとえば、事業用資産として暗号資産を保有し、それを用いて棚卸資産などを購入する場合です。
暗号資産の定義
ここまで話してきた暗号資産は、ビットコインやイーサリアムなど、
元々仮想通貨と呼ばれていたものを想定してください。
NFTに関しては、税務署からの別途取り扱い情報が出ているため、異なる場合があります。
NFT取引と税金
さてNFTの税務です。
自分で作成したCGにNFTを設定し、それを販売した場合、
税金はどうなるでしょうか?
NFTの場合も、基本的には雑所得になりますが、
事業所得になる可能性も高いです。
もし、サラリーマンが副業として
少量のNFTを扱う場合、雑所得となる可能性が高いですが、
事業の一環としてNFTを発行している場合は
事業所得と見なされる可能性が高くなります。
NFTは、自社の様々なアナログ商品・サービスと
連携が可能であるため、通貨的な扱いの暗号資産とは異なります。
これらのケースの取り扱いは複雑であるため、専門家への確認がおすすめです。
NFTの転売と税務
次に購入したNFTを転売した場合はどうでしょう?
法人の場合は、益金・損金に変更はありませんが、
個人の場合は原則として譲渡所得になります。
これは、絵や土地など、資産的価値のあるものを購入し、
利益を得るために売却するケースと同様です。
暗号資産がお金のように扱われるのとは違い、
NFTは資産としての考え方が基本になります。
譲渡所得となると税金計算が複雑になります。
NFTの転売は総合課税の譲渡所得となり、
特別控除額50万円が適用されます。
また、他の所得との損益通算も可能ですが、
生活に通常必要でない資産の場合、赤
字であっても損益通算はできません。
基準は、1つ30万円を超えるかどうかです。
営利目的で継続的に転売を行う場合、
事業所得または雑所得になる可能性があります。
産にかかる法律は未確定な部分が多くあります。
本記事は書いたときの法律や通達をもとにしているため、
後日変更になることがあります。
ご注意ください。