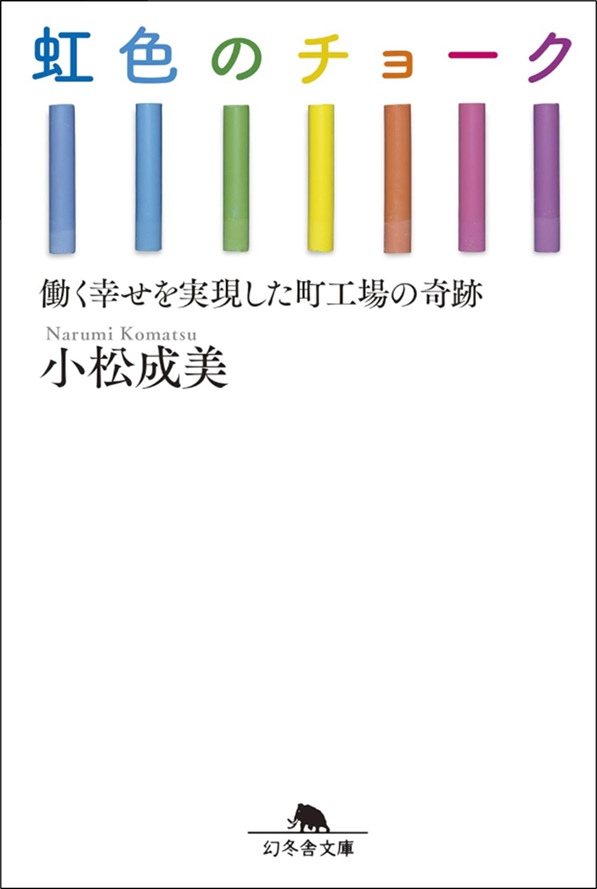あいさつ
大澤賢悟です。 noteに、ChatGPTを活用して求人を作成する方法をまとめた記事を無料公開しました。noteで検索する場合は、マガジンを選択し、「100万円かかる」で検索していただくと見つかります。
Facebook、X、Instagram、Threadsからもリンクしており、弊社ホームページにも同内容を掲載しています。書籍をイメージして執筆したところ、総文字数は6万字を超えました。内容は、AIが求人情報を整理し、文章を作成し、さらに採用用のホームページまで生成する一連のプロセスを具体的に解説しています。求人作成は、厳密さよりも柔軟な表現力が求められる分野であり、生成AIとの相性は非常に良いと感じています。しかもAIを使えば、掲載後の反応を見ながらすぐに書き直すことも可能です。ハローワークやIndeedなどで求人を出しても応募が少ない場合、きっと新しい発見があると思います。生成AIの無料コースを使えば、費用はかかりませんので、ぜひ一度試してみてください。もし良ければ、周りの方にもシェアしていただけると嬉しいです。
そのパソコン、本当に大丈夫?――2025年10月、サポート終了がもたらす経営リスク
皆さま、会社で使っているパソコンやソフトが、実は大きなリスクになっていることをご存じでしょうか。特に注意しなければならないのは、Office 2019とWindows 10です。この二つはいずれも、2025年10月14日でマイクロソフトによるサポートが終了しました。サポートが終わるということは、使い続けても新たな脆弱性(ソフトの弱点)の修正プログラムが提供されなくなるという意味です。つまり、もしそこに使われているソフトやOSが攻撃者に狙われる対象となっても、守る手立てがどんどん薄くなっていくということです。実際、国内ではアスクルがランサムウェア(身代金要求型ウイルス)に感染し、受注や出荷が止まるなど大きな混乱に陥りました。また、アサヒビールも同様のサイバー攻撃を受け、国内の注文や出荷に影響が出た報道があります。大企業ですらこうした被害を受けているということは、守りにくい中小・零細企業だからこそ、危機感をもって対策すべき状況というわけです。特に中小企業は、大企業と比べて人員も予算も限られており、サイバーセキュリティ体制を整えるのが後回しになりがちです。サポート切れのソフトを入れたまま、日常業務を続けていれば、攻撃者にとって格好の入口になってしまう恐れがあります。こうしたリスクを放置せず、まずは現状を把握することが第一歩です。社内で使用しているパソコン・タブレット・ソフトのバージョンやサポート状況をリスト化し、どれを優先して更新すべきか優先度をつけましょう。そして、原則としてWindows 10やOffice 2019を後継バージョン・サービスに切り替えていくことが望まれます。どうしても残す端末がある場合には、「台数を限定」「使用期限を定める」「ネットワークを分ける」といった例外運用ルールを明確にしておくのが有効です。さらに、バックアップ体制を今一度見直すことも欠かせません。メールや添付ファイルが侵入経路になるケースも多いため、なりすましメール対策(DMARC/SPF/DKIM)や多要素認証(MFA)、最小権限でのアクセス管理を導入し、社員やパート・アルバイトの皆さまにも「何が危ないか」「自分にできることは何か」を共有しておきましょう。中期的には、会計・販売・勤怠などの主要ソフトが新しいOS・Office環境で動くかどうかを検証し、社内ネットワークを古い端末用ゾーンと重要データ用ゾーンに分割する「セグメンテーション」も検討してください。そして、万一の際に備えた連絡体制・取引先への通知手順などを具体的に定め、年に一度はインシデント対応演習を実施することで、停滞ではなく“止まらない仕組み”を作ることができます。「まだ動いているから安心」という考え方は、実は最も危険です。サポート切れ端末は、まさに“スプリンクラーが動かない建物”で営業しているようなものです。守りを固めることは、売上を上げることと同じくらい重要な経営の一部です。今日から一歩ずつでも行動を始め、未来の安心を手に入れましょう。
なお、弊社で申告書・総勘定元帳等をお渡しするにあたって、USBメモリを用いていましたが、今後は、徐々に廃止していく予定です。USBメモリはファイアウォールを経由せずパソコンにつながるためウイルスやランサムウェアの感染経路となることがあり、また、紛失・盗難によって情報漏洩が起きるリスクがあります。今後はリスク管理の観点から、クラウドを活用していく予定ですので、よろしくお願いいたします。
急成長するアナログAI
いま企業が直面している課題の一つに「人手不足」があります。工場では技能を持つ人材が減り、物流では離職率が高まり、介護や小売の現場でも担い手が不足しています。こうした分野で導入が進んでいるのが「アナログAI」と呼ばれる技術です。生成AIが言葉や画像を生み出すのに対し、アナログAIは現実世界で学び、動き、人の代わりに作業をこなすAIです。
たとえば中国の研究チームが開発した「HoST」は、転んでも自律的に立ち上がる人型ロボットを可能にしました。蹴られても鉄球をぶつけられても、再び立ち上がる。その耐久性は災害救助や介護の現場で大きな力を発揮する可能性があります。また日本ではATRや京都大学が「サイボーグAI」を開発し、スケートボードの動きを人型ロボットに学習させることに成功しました。高度なバランス制御は、危険作業やリハビリ支援に応用できると期待されています。一方、民間企業も動きを加速させています。テスラは自社の将来価値の大半をロボット事業が担うと公言し、人型ロボット「オプティマス」を開発中です。日本ではセブン-イレブンが2029年までに人型AIロボットを全国店舗に導入する計画を立て、調理や陳列などをロボットが担う姿を現実のものにしようとしています。
アナログAIが急成長している背景には三つの理由があります。第一に、現実世界のデータが不可欠になったこと。ネット上にある情報は全体の一割程度にすぎず、工場や店舗の経験知こそがAIの性能を高める源になります。第二に、アルゴリズムの進化です。強化学習や模倣学習、生成AIの組み合わせにより、複雑な動きをリアルタイムで制御できるようになりました。第三に、社会的な必然性です。人材不足を放置すれば事業が立ち行かなくなる現場が増えており、AIの導入は選択肢ではなく必要条件になりつつあります。
もちろん課題もあります。人と同じ空間で安全に動作させるには、まだ技術的な精度が不足しています。導入コストも高く、中小企業には手が届きにくいのが現状です。さらに、現場データを海外企業に提供すれば、日本の競争力を損なうリスクもあります。それでも、アナログAIのメリットは大きいといえます。人間の設計した環境にそのまま適応できる汎用性、低消費電力チップによる長時間稼働、そして倒れても起き上がる安定動作。こうした特性は産業から医療、教育、災害対応まで幅広く応用できます。
アナログAIは今後10年で社会に確実に浸透していく技術です。 Amazonでは物流現場のロボットで60万人の人員削減、AI技術で管理部門も1割に当たる3万人の削減を予定しています。2020年代後半には物流や小売で深夜無人運営が始まり、2030年代初頭には介護や教育の現場でも日常的に利用されるでしょう。私たちがコンビニに立ち寄るとき、病院で診察を受けるとき、あるいは災害時に支援を受けるとき――そこにはすでにアナログAIが働いている。そうした未来が現実に近づいています。現在は人手不足ですが、人余りの時代が来るかもしれません。その時、人に携わる様々な業務も不要になっていくかもしれません。
控除証明書は金券です!
年末が近づくこの時期になると、保険会社や金融機関などから、生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・社会保険料控除証明書・住宅ローンの残高証明書などが続々と届き始めます。これらは、年末調整や確定申告で所得控除を受けるために欠かせない大切な書類です。提出を忘れてしまうと、税金が本来よりも多く計算されてしまい、結果的に払い過ぎになることもあります。たとえば生命保険料控除では、契約内容によって最大12万円の所得控除が受けられる場合もあります。これを提出し忘れると、その分だけ税負担が増えてしまうのです。また、住宅ローンを利用されている方に届く「住宅借入金等特別控除証明書(住宅ローン残高証明書)」も非常に重要です。これをもとに住宅ローン控除の金額を計算しますので、紛失すると再発行の手間がかかります。届いた証明書は封筒ごとまとめてクリアファイルなどに入れ、「控除証明書」などのラベルを貼っておくと安心です。勤務先への提出や確定申告の際にすぐ取り出せるように、今のうちに整理・保管しておきましょう。